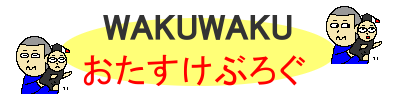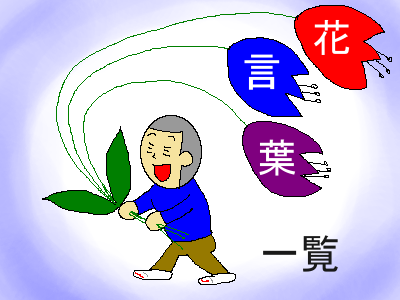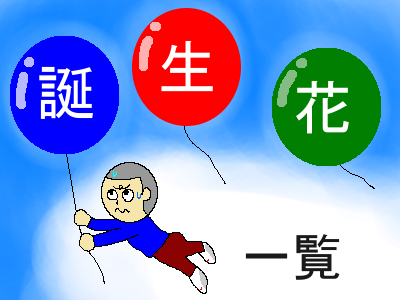花や草木に特別な意味を持たせる花言葉![]()
花好きな母親に育てられたためか、私は昔から「花」と「花言葉」が大好きなんです。
そんな花言葉好きな私がいつもモヤモヤとすることがあるんです。それは…
花言葉って、なんでこんなに複雑でややこしいの?
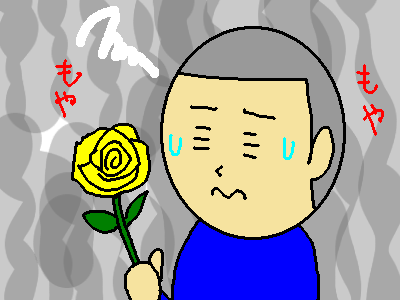
同じ花にたくさんの花言葉が存在したり、真逆のような意味が付いていたり…花言葉って複雑すぎるんです。私と同じようにモヤモヤしている人も多いのではありませんか?そこで…
そんな鬱屈(うっくつ)した気持ちをスッキリしてもらうため「花言葉の由来や起源」を解説いたします。
花言葉の由来や起源を知れば、なぜ花言葉が複雑なのか?しっかりと納得できるんですよ。是非ご覧になってくださいね。
Contents
花言葉の起源とその由来
![]() 花言葉の起源には諸説ありますが、その中でも有力なひとつの説をご紹介します。
花言葉の起源には諸説ありますが、その中でも有力なひとつの説をご紹介します。
花言葉の起源とは?
花言葉の起源は、アラビア地方で古くから行われていたセラム(selam)という風習だと言われています。
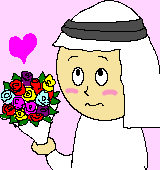
それぞれの花に意味を持たせ、それを組み合わせることで「花の手紙」になっていたそうですよ。
そんなセラムの風習がヨーロッパへと伝わります![]()
花言葉の風習がヨーロッパへ
花言葉の風習がヨーロッパに伝わったのは、今から約300年前の18世紀のことです。その立役者となったのがつぎの二人です。
- メアリー・ウォートリー・モンタギュー
- ラ・モトライエ
順番にみていきましょう。
メアリー・ウォートリー・モンタギュー

メアリー・ウォートリー・モンタギュー(Mary Wortley Montagu 1689-1762)、イギリスの詩人、手紙文学の女流作家。
1716年、イギリスの駐トルコ大使夫人としてトルコに渡った彼女は、イギリスの友人に向け、トルコの風習を紹介する手紙をたくさん送っています![]()
手紙のなかでは「トルコの花言葉の風習」も紹介されていて、これがヨーロッパに花言葉を伝えた最初の記録だと言われています。
送られた手紙はモンタギューの没後の1763年に「トルコ書簡集」として出版されています。
ラ・モトライエ
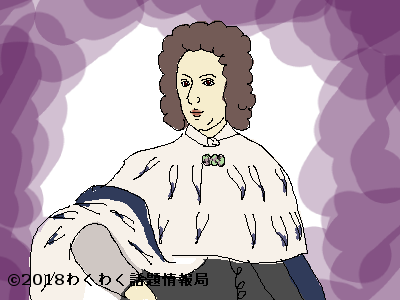
スウェーデン国王カール12世
ラ・モトライエはスウェーデン国王カール12世の部下でした。
1709年、カール12世はポルタヴァの戦いでロシアに敗れてトルコへ亡命します。その後、5年間トルコに滞在したのちスウェーデンに帰国を果たしました。
ラ・モトライエもまた国王と共にトルコに亡命し、約5年間の亡命生活でトルコの花言葉の風習を学び、それをヨーロッパに持ち帰ったと言われています![]()
こうしてヨーロッパに伝わった花言葉の風習ですが、当時のヨーロッパの人たちはそれほど関心を示しませんでした。花言葉が人気を博すのは、それから約100年後のフランスです。
フランスでブームが起こる
19世紀の初頭…フランスで花言葉のブームが起こります。そのきっかけは一冊の本の出版でした。
それが…
シャルロット・ド・ラツール著の花言葉(Le Langage des fleurs)です。
Amazonのリンクです。
1818年に出版されたこの本はフランスで18版も重ねるほどの人気となり、アメリカやスペインでは海賊版が出回るほどでした。また類似本も多数出版されるなど花言葉が大流行したんです。
草花の性質を用いて、誰かのことを称賛したり、時には、非難や悪口を書いて楽しんでいたそうです。
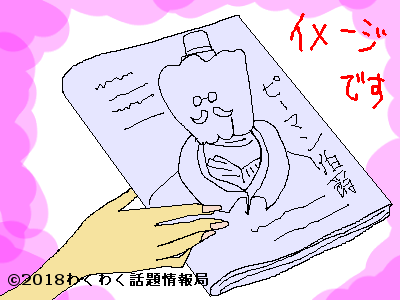
フランスではそういった土台もあって花言葉が大ブームとなったんです。
ヨーロッパ全体にブームが広がった花言葉の風習はやがて日本へと伝わります![]()
花言葉の風習が日本へ
花言葉が日本へと伝わったのは明治時代のことです。
1886年、『泰西礼法』(ルーイズ・タルク著、上田金城訳)という本が出版されます。この本が日本で最初に花言葉を紹介した書籍だと言われています。
1910年、『花』(江南文三、与謝野晶子著)が出版されます。こちらは日本初のまるごと一冊が花言葉を扱った本です。この本では詩人で文芸雑誌「スバル」の編集者でもあった江南文三(えなみぶんぞう)が花言葉を解説しています。
そして・・・どんどん複雑でややこしくなっていくんです。
とても複雑な日本の花言葉
インターネットで花言葉を調べていると、ひとつの花に複数の言葉が付いていたり、同じ花なのにまるで違う意味の言葉が付いていたりします。
例えば…ひまわりには「![]() いつわりの富・にせ金貨・
いつわりの富・にせ金貨・![]() あなたを見つめる・崇拝・あなたは素晴らしい・愛慕・光輝・憧れetc…」といった感じで花言葉が付いています。なので…
あなたを見つめる・崇拝・あなたは素晴らしい・愛慕・光輝・憧れetc…」といった感じで花言葉が付いています。なので…
…と悩んでしまう方も多いと思います。でも…
何故こんな複雑でややこしい事になったのでしょうか?
どうして花言葉はこんなにややこしいの?
![]()
![]() 花言葉はヨーロッパからブームが起こりました。なので…もともと花言葉はヨーロッパの人たちにピッタリなものになっているんです。
花言葉はヨーロッパからブームが起こりました。なので…もともと花言葉はヨーロッパの人たちにピッタリなものになっているんです。
そんなヨーロッパの花言葉が世界各国に伝わると、その国ごとの文化や歴史、そして花の特性に合った花言葉がどんどん追加されていくんです。例えば…
そして現代でも…
もともとが曖昧な存在ですからね。ただしそれが浸透するかどうかは別問題です。
そして…ネットで世界中と情報交換できるような時代になり、日本の花言葉は世界中のものが入り混じっている状態になっているんです。
複数の花言葉がある場合はどうすれば良いの?
![]() あくまでも当ブログの見解なのですが・・・
あくまでも当ブログの見解なのですが・・・
“ひまわり”を例に紹介すると…
こんな感じで贈ればバッチリだと思います。
ただし!
ひまわりのように悪い意味の花言葉が同時に付く場合には…
…なんてことになったら大変です。誤ったメッセージが相手に伝わらないように注意しましょう。対策としては…
このようにして贈れば安心ですし、もらった相手もきっと喜んでくれると思いますよ。
あとがき・・・
花言葉の由来とその起源についてご紹介しました。
今回は「花言葉の由来を起源」を調べてみましたが『花言葉はとても曖昧でアバウトな存在なのだなぁ…』とあらためて感じました。でも…そのような存在だからこそ、花言葉は気楽に楽しめるのでしょうねぇ。
みなさんも花を観賞するときに、サッと「花の名前、花言葉」でググってみてね。昔の人たちが、どんな気持ちでその花を見ていたのかが分かって楽しいですよ。
是非お試しあれ~
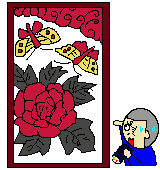
記事:けいすけ