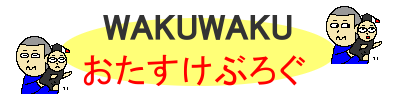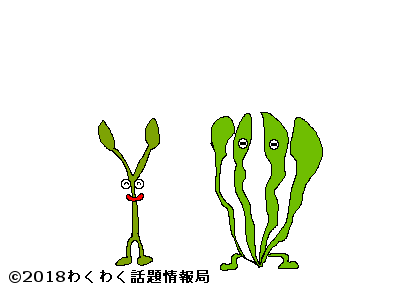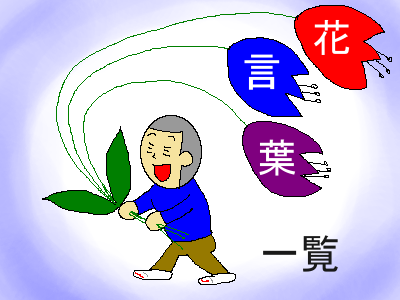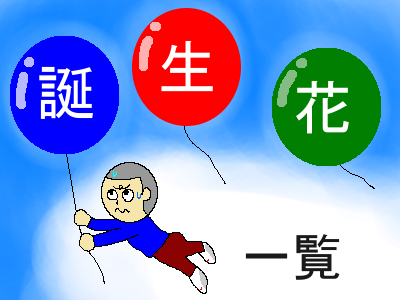春の七草のひとつです。葉や茎に生えた白い綿毛のうえに、黄色い粒のような花を咲かせます。ゴギョウ(御形)という名前でもお馴染みですよね。
今回はそんなハハコグサの花言葉をご紹介します。実はハハコグサには…
母と子の愛の花言葉が付いているんです!
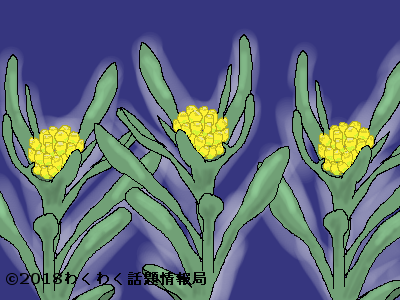
この記事を読めば、ハハコグサの花言葉とその「由来」や「意味」を知ることができます。
あわせて「花情報」「名前の由来」についてもご紹介しますので是非ご覧ください。
ハハコグサの花言葉
![]() それでは早速、ハハコグサの花言葉をご紹介しますね。その花言葉とは…
それでは早速、ハハコグサの花言葉をご紹介しますね。その花言葉とは…
ハハコグサは漢字で母子草と書きます。
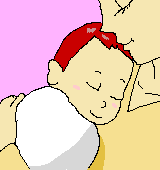
そう・・・お母さんと子供なんです。
ハハコグサ(母子草)という名前の由来は、一説に、白い綿毛のうえに黄色い粒のような花が咲く姿が、母が子をやさしく抱くように映るためだと言われています。
そんな…ハハコグサが母が子を抱くように花を咲かせることから「いつも想っています、忘れない、無償の愛」の花言葉が付きました。
ハハコグサ(母子草)を楽天市場で探すならこちら>
これは花言葉はありませんが、ハハコグサには別の意味もあるんですよ。それは…
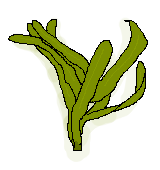 「仏のからだ」
「仏のからだ」
ハハコグサの花情報
ここではハハコグサの花をより身近に感じていただけるようにハハコグサの花情報を3つご紹介しますね。
- ハハコグサの花情報
- ハハコグサの名前の由来
- ゴギョウ(御形)の名前の由来
それでは順番にどうぞ!
ハハコグサの花情報
学 名= Gnaphalium affine
英 名= Jersey cudweed
和 名= ハハコグサ(母子草)
別 名= ゴギョウ(御形)または“オギョウ”と読みます。
原産地 = 日本、東南アジア
色 = 黄
開花時期= 3月~5月
誕生花 = 3月1日
ハハコグサの名前の由来
![]() 学名はGnaphalium affineです。Gnaphaliumとはギリシャ語でむく毛(gnaphallon)という意味です。茎や葉に生える綿毛の姿が、獣の毛のようだってことなんでしょうね。
学名はGnaphalium affineです。Gnaphaliumとはギリシャ語でむく毛(gnaphallon)という意味です。茎や葉に生える綿毛の姿が、獣の毛のようだってことなんでしょうね。
和名のハハコグサ(母子草)の名前の由来には諸説ありますので3章に分けてご紹介しますね。
①花の姿から・・・
花言葉のところで解説しましたが・・・

ハハコグサは茎や葉が白い綿に覆われていて、その姿が子供を抱く母親を連想させるため、この名前が付いたと言われています。
![]() 繰り返しなのでイラストも再利用です。
繰り返しなのでイラストも再利用です。
②転訛した・・・
ハハコグサの茎や葉は、白い綿毛で覆われています。
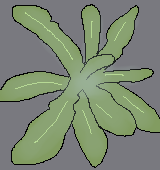
かつてはその姿をほうけだつ(伸びて立つ)と言っていました、そこからホウコグサと呼ばれるようになり、だんだんと転訛してハハコグサになったと言われています。
ホウケダツ→ホウコグサ→ハハコグサ![]()
③節句の行事から・・・
むかし・・・3月3日の上巳の節句(じょうしのせっく)には、母子の人形と母子餅と呼ばれる草餅を飾って、身の穢(けがれ)れを清めていたそうです。
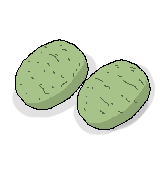
草餅といえば、現在ではヨモギを材料にしたお餅のことですよね。しかし昔はヨモギではなくハハコグサウを使っていたんです。
そんな母子餅の材料に使われていたことが由来となりハハコグサになったと言われています。
ゴギョウ(御形)の名前の由来
ハハコグサ(母子草)は、別名でゴギョウ(御形)とも呼ばれています。春の七草のひとつとして有名なので、ゴギョウという名前の方がピンとくる人も多いですよね。
![]() そんなゴギョウ(御形)の名前の由来をご紹介しますね。
そんなゴギョウ(御形)の名前の由来をご紹介しますね。
日本には人形流し(ひとがたながし)という風習があります。これは人に見立てた紙製の人形を川に流して、からだの厄や穢れを流そうとする風習なんです。そして…
その人形の代わりに・・・
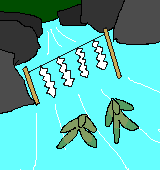
ハハコグサを流す風習もあったそうなんです。
そのため“人形”という意味のあるゴギョウ(御形)という名前が付けられたと言われています。
あとがき・・・
ハハコグサの花言葉をご紹介しました。
それでは最後にもう一度、ハハコグサの花言葉を繰り返しご紹介しますね。
それじゃ・・・
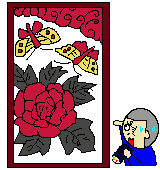
記事:けいすけ