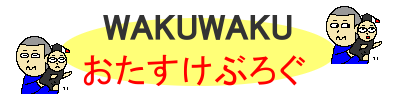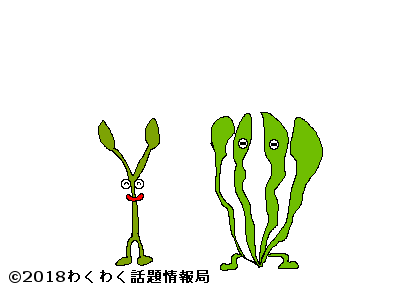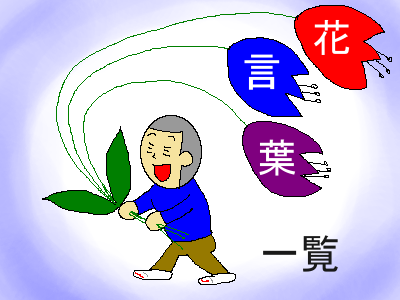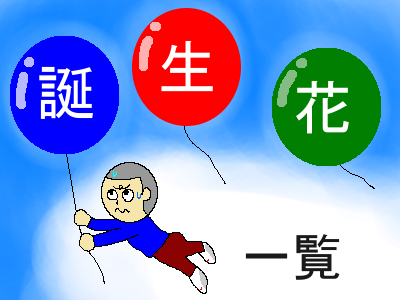けいすけ
春の七草が好き!そんな管理人の「けいすけ」です。今回ご紹介するのはこれ!
田んぼの畔(あぜ)などに生えて、夏に白い花を咲かせます。素朴で味わいのある花なのです。でも…私にとっては七草がゆのイメージが強いかなぁ。なにぶん食いしん坊なので…
今回はそんな素朴な花が咲くセリの花言葉をご紹介します。実はセリには、
日本人の美徳のような花言葉が付いているんです!

この記事を読めば、セリの花言葉とその「由来」や「意味」を知ることができます。
実は、花言葉の由来にあの聖徳太子が関係するともいわれているんです。そんな「聖徳太子にまつわるお話」もご紹介しますね。そのほか「花情報」「名前の由来」などもお届けしますのでお楽しみに。
けいすけ
由来となった聖徳太子のお話って、どんなんやろうね?ここからは先生とお芝居ふうにお伝えします。
スポンサーリンク
セリの花言葉
![]() それでは早速、セリの花言葉をご紹介しますね。その花言葉とは…
それでは早速、セリの花言葉をご紹介しますね。その花言葉とは…
※高潔とは、気高く穢れがないこと。清廉(せいれん)とは、私利私欲に走らず、心が清らかなことです。
けいすけ
むむむ・・・日本人の美徳のような花言葉ですね。どうしてこの花言葉が付いたのですか?
セリには白い清楚な花が咲きますが、それが繁殖する場所って田の畔(あぜ)や川べりなどなんです。そう…

泥のあるような場所に根を這(は)わせながら、たくましく成長しているんです。
けいすけ
「清廉」に「高潔」かぁ・・・素敵な響きをもったメッセージですね。プレゼントにもピッタリだ。
花言葉の由来には別説もあって、あの聖徳太子が関係しているとも言われているんですよ。そのお話をご紹介しますね。
むかし、むかしのお話です。
聖徳太子が、推古天皇のもとへ向かうため、膳夫(かしわで)の地を通っていました。
※膳夫とはいまの奈良県橿原市

町の人々は、聖徳太子が通り過ぎるのを、じっと伏して待っています。ところが…

たった一人、若い娘がこちらに背を向けて、川辺で仕事を続けているのでした。それを不審に思った太子は、娘に問いかけます。
何をしているのですか
娘は太子の存在に初めて気付いたようでした。そして太子の問いに、病気の母のためにセリを摘んでいるのだと言います
娘の清らかで美しい容姿、そして母をいたわる優しい心、太子は一目で娘を好きになり、妃(きさき)として娶(めと)ることを決めたのでした。
娘の名前は菩岐岐美郎女(ほききみのいらのつめ) 別名 芹摘姫(せりつみひめ)とも呼ばれています。聖徳太子の4人の妃の中で、もっとも貧しい身分の出身です。しかし太子からいちばんの寵愛(ちょうあい)を受け、子供もいちばん多かったと言います。
おしまい
このお話に由来してセリの花言葉「貧しくても高潔、清廉で高潔」が付いたともいわれているんです。
けいすけ
芹摘姫は「貧しくても高潔」「清廉で高潔」どちらの花言葉にもピッタリと当てはまる女性ですね。
セリ(芹)を楽天市場で探すならこちら>
これは花言葉では無いのですが、セリには別の意味もあるんですよ。それは…
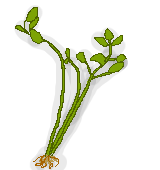 「競り勝つ」
「競り勝つ」
セリと言えば、春の七草のひとつで七草粥として食べる野草でもありますよね。七草にはそれぞれ意味があって、セリには“競って勝ちますように”そんな願いが込められています。
花言葉の清廉に合わない感じもしますが、お互いが努力をして競争するのですから良い意味だと思います。
スポンサーリンク
セリの花情報
ここではセリの花をより身近に感じていただけるようにセリの花情報を3つご紹介します。
- セリの花情報
- セリの名前の由来
- 和歌に詠まれるセリ
それでは順番にどうぞ!
セリの花情報
分 類= セリ科セリ属
学 名= Oenanthe javanica
英 名= Water dropwort、Japanese parsley
和 名= セリ(芹)
別 名= 白根草
原産地 = 日本、中国、朝鮮半島、アジアオセアニア
色 = 白
開花時期= 7月~8月
誕生花 = 1月7日
近所の散歩道にて…

名古屋市天白区の八事霊園の片隅に咲いていました
学 名= Oenanthe javanica
英 名= Water dropwort、Japanese parsley
和 名= セリ(芹)
別 名= 白根草
原産地 = 日本、中国、朝鮮半島、アジアオセアニア
色 = 白
開花時期= 7月~8月
誕生花 = 1月7日
近所の散歩道にて…

名古屋市天白区の八事霊園の片隅に咲いていました
セリの名前の由来
学名はOenanthe javanicaです。Oenantheとは、ギリシャ語で酒(oinos)と花(anthos)の意味があります。お酒の花ってことかな?
和名のセリ(芹)とは・・・

セリの若葉が一か所で競り合うように生えるそんな姿から付けられました。
別名ではシロネグサ(白根草)とも呼ばれます。これは…
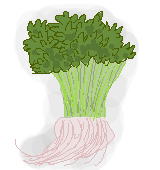
長く伸びる白い根の様子から付きました。
スポンサーリンク
和歌に詠まれるセリ
古くから日本に自生しているセリは、とても身近な存在で、和歌などにも歌われています。万葉集にこんなやり取りがありますのでご紹介しますね。
葛城王「万葉集」
あかねさす 昼は田たびて ぬばたまの 夜のいとまに 摘める芹これ
(現代語訳)
昼は宮仕えで忙しかったので、何とか夜に暇を見つけて、摘んできたセリなんですよ、これは!
(現代語訳)
昼は宮仕えで忙しかったので、何とか夜に暇を見つけて、摘んできたセリなんですよ、これは!
葛城王(かつらぎのおおきみ)からセリをもらった、女官が返歌します。
薩妙観命婦「万葉集」
ますらをと 思えるものを 太刀はきて かにはの田井に 芹ぞ摘みける
(現代語訳)
あなたは大変偉い方だと思っていましたが、刀をさし、蟹のようになりながら、田でセリを摘んでおられたのですか
(現代語訳)
あなたは大変偉い方だと思っていましたが、刀をさし、蟹のようになりながら、田でセリを摘んでおられたのですか
あとがき・・・
セリの花言葉をご紹介しました。
それでは最後にもう一度、セリの花言葉を繰り返しご紹介しますね。
―セリの花言葉―
 貧しくても高潔
貧しくても高潔
 清廉で高潔
清廉で高潔
けいすけ
どちらも素敵な花言葉なので大事な人へのプレゼントに使ってみてくださいね。
それでは・・・
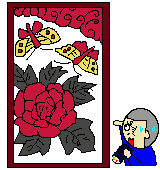
記事:けいすけ
広告